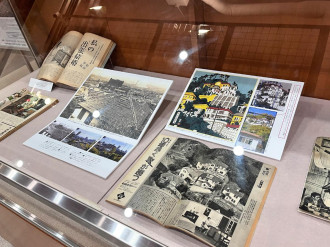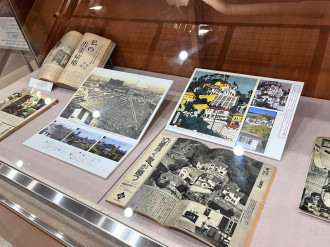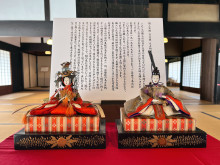ワークショップ「T3パズル(テセレーション)を使ってオリジナル作品を作ってみよう!」が7月1日、大阪商業大学 ユニバーシティ・コモンズリアクト(東大阪市御厨栄町1)で開かれた。
同大学の谷岡一郎学長が考案した「T3パズル」。「T3」は、「トライアングル」「テセレーション(敷き詰め図形)」「タイリングパズル」の意味で、表裏で柄の異なる1種類の正三角形ピースを敷き詰めて図形や模様を創作する。児童教育における数学的センス、芸術性を育むことを狙いとして考案された。2014(平成26)年に開発し、当初は横浜にある科学館に展示していたが、「家に持って帰ってやりたい」と販売を望む声が多く、2017(平成29)年に78枚のピースをセットにした「T3パズル」の販売を開始した。
ピースは、片面の4分の1が白い三角形でその他の部分には色が付いているおり、裏面はその逆の配色になっている。2枚をつなぎ合わせてダイヤ形を作るだけでも36通りの並べ方があり、販売元の日本テセレーションデザイン協会代表の荒木義明さんは「実際に触った人がルールやこつを見つける自由度がある。算数に近いが正解がなく、全部が正解。算数や数学は教科書の問題を解くだけでなく、たくさん触ることで分かる要素もある」と話す。
ワークショップは全国の小学校や科学館などで行っており、東大阪では昨年12月に続き2回目。荒木代表が「表裏で柄が違うので、いろいろな並べ方をして想像力を豊かにして何に見えるか考えてほしい」と問題を出し、子どもたちは元気よく答えた。その後は実際にピースを並べて、2枚でダイヤ形、6枚で六角形などを作って、それぞれどのような模様ができるかを発表し、その後は自由に創作をした。
参加した小学5年の女子児童は「最初はイルカを作ろうと思ったが難しく、ウサギを作ろうとピンクのパズルにしたけど顔が横長になったのでパンダを作った。最初作ろうと思っていたものが作れなくても、違うものができるのが面白かった」と話す。
ワークショップ終了後、荒木さんは「それぞれの工夫があって、こんなやり方あるんだって毎回驚く。自分の考え方を実現できるという気持ちがあればOK。作れると思ったらどんどんできるので、T3パズルでその体験をしてほしい」と話した。
同協会では1年に2回、T3パズルで作った作品を募集するコンテストを開催。現在、「T3サマーコンテスト2023」を開催中で、作品は紙版のT3パズル、ウェブアプリのいずれかで受け付ける。募集は9月4日24時まで。