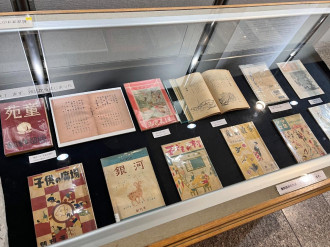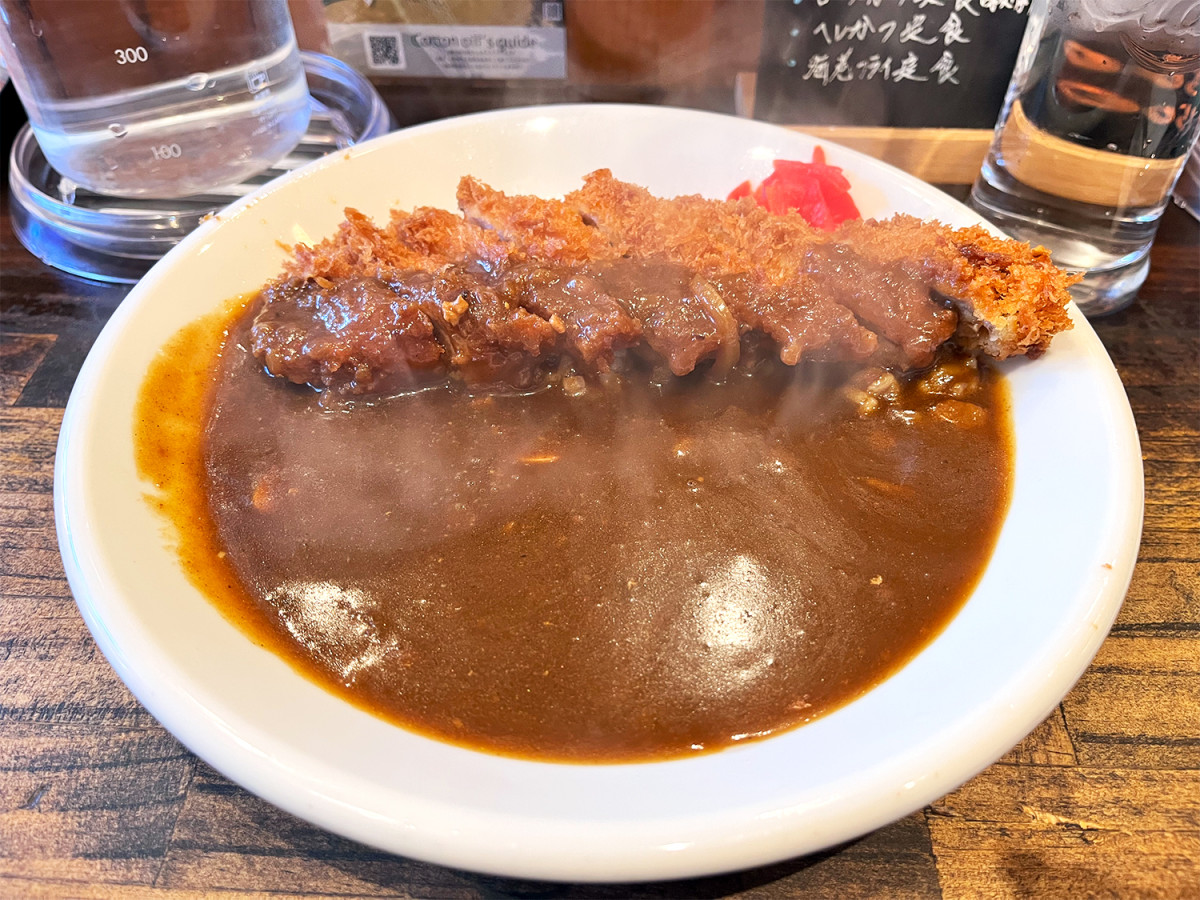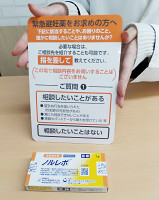関西学院大学(西宮市)経済学部栗田研究会の学生が企画したイベント「こーばの未来会議」が3月20日、COBA(東大阪市岸田堂西2)で開催された。
「こーばの未来会議」は、東大阪の町工場が抱える課題を高校生と大学生が知り、課題の解決に挑戦するイベント。関西の地域活性化や中小企業の課題解決に取り組む栗田研究会(ゼミ)関西企業班が産業集積地である東大阪に着目し、「若者と企業の接点を作る」「企業間・学生間のつながりを作る」「東大阪工業地域が新しいことに挑戦するきっかけを作る」「高校生が大学での学びを先取りする」の4つを目的に掲げ、企画した。
同イベントには、アルミ建材設計製作施工「三島硝子建材」(岸田堂西2)、メガネレンズ製造販売の「昭和光学」が運営するメガネとカフェの店「レンズビーンズ」(俊徳町2)、墓石製造「大阪石材工業」(水走3)、クラフトビール醸造所「INGRY MONGRY(イングリーモングリー)」(中新開2)の4社と高校生5人、大学生17人が参加。3月15日・16日には4チームに分かれて担当企業に滞在し、各企業の課題の発見、解決策の立案を行うワークショップを行った。代表で関西学院大学経済学部4年の大岩祐生さんは「昨年4月から活動を始めて25社ほどの企業を訪問し、夏ごろにこのイベントをしたいとオープンファクトリー『こーばへ行こう!』の事務局を担当しているCOBAに相談した」と振り返る。当日は、高校生がワークショップの様子や考えた解決策をショートムービーで発表した。
INGRY MONGRYの「若者にクラフトビールが知られていない」という課題に挑戦したチームは、大学を卒業する先輩にクラフトビールと栓抜きをプレンゼントする企画を実施した。
地域に貢献したい考えがある三島硝子建材は、地域の子どもが犯罪に巻き込まれそうになった時に保護を求めることができる「こども110番の家」運動に協力しており、「こども110番の家に入りやすくするにはどうすればいいか」という課題を出した。高校生たちは「会社なので子どもや一般の人は入りにくいため、地域の子どもたちが宿題をしにきたり、大人の人と話をしたりする『てらこもんず』という場を作るのがいいのでは」と提案。同社では8月に「てらこもんず」を実施することにしたという。
レンズビーンズを担当したチームは、製造過程で出る廃棄レンズの活用法を考案。ムービーでは、砕いて表札やメモリアルプレート、ジェルキャンドルなどにリユースしようと試行錯誤する様子を映し出し、「2日間で完成しなかったが工場に対する愛が深まったのでこれからも研究を続けたい」と意気込む。
墓じまい後の墓石や端材の有効活用について考えた大阪石材工業担当チームは、職人の技術を知ってもらうためのショールームを活用したワークショップの開催や、石で作るキャンプギアなどを提案した。
審査員として参加した高校生百貨店を運営するCo.to.hana代表の西川亮さんは「高校生の活動はインプットする機会が多いが、ただ発表するだけでなく、短い期間で実践を繰り返しながら発表したところが素晴らしい」と評価した。